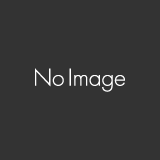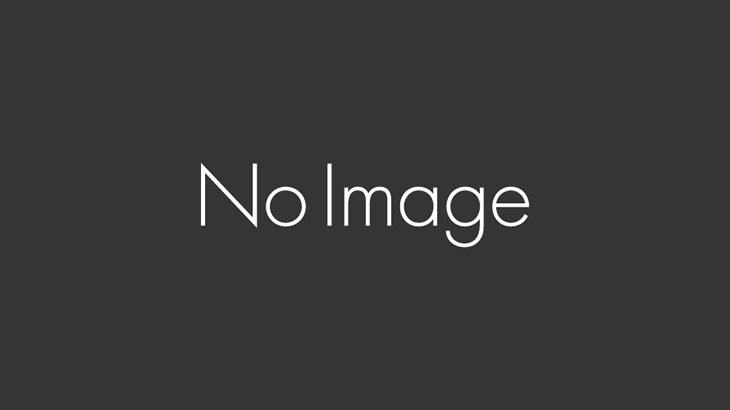「余命半年」から18年たっても元気…がんの「余命宣告」はなぜ大きく外れることがあるのか
「余命半年」から18年たっても元気…がんの「余命宣告」はなぜ大きく外れることがあるのか
※本稿は、和田洋巳『がん劇的寛解』(角川新書)の一部を再編集したものです。
■がんはどうやってヒトを死に至らしめるのか
そもそも、がんはどのようにして宿主であるヒトを死に至らしめるのでしょうか。まず、この点について掘り下げていきましょう。
標準がん治療では「治らない」とされるIV期の固形がんを例に取ると、多くの場合、患者は原発巣から転移した他臓器が機能不全に陥ることによって死に至ります。そして、転移巣で起こる臓器不全には、1つの臓器が致死的な状態に陥る単臓器不全と複数の臓器が致死的な状態に陥る多臓器不全の2つのケースがあります。
単臓器不全について言えば、転移巣の増大によって、例えば腎臓が機能不全に陥る腎不全、肝臓が機能不全に陥る肝不全などがあります。内臓の腹膜に散らばった豆粒のような転移巣、いわゆる腹膜播種(はしゅ)が増大して消化管を圧迫した結果、消化管の通過障害によって死に至るケースなども、単臓器不全に含めていいでしょう。
一方、転移を来した複数の臓器が同時多発的に機能不全に陥る多臓器不全は、多くの場合、極量の抗がん剤による乗り換え治療を続けた結果として起こってきます。抗がん剤治療は臓器に転移があるか否かを問わずヒトの全細胞に絨毯爆撃を加えていくような荒療治であること、またがんは抗がん剤耐性を獲得していくたびに一段と狂暴化して猛烈にリバウンドしていくことが、結果的にしばしば多臓器不全をもたらすのです。
■がんが体内にあるだけで死ぬことはほぼない
もっとも、私は抗がん剤治療を全面的に否定しているわけではありません。「抗がん剤も使い方次第」というのが私の基本的なスタンスです。例えば抗がん剤の使用量を減量した場合、あるいは抗がん剤治療を途中で中止した場合、さらには抗がん剤治療そのものを行わなかった場合などでは、仮に複数の臓器に転移があったとしても、患者の多くは多臓器不全ではなく、最初に陥った臓器の機能不全、すなわち単臓器不全で死に至ります。
では、がんが宿主であるヒトを死に至らしめるこれらのプロセスを逆方向から眺めた場合、どのような風景が見えてくるでしょうか。
抗がん剤はその強い毒性によって患者にしばしば副作用死をもたらしますが、がん細胞そのものがヒトを死に至らしめる毒素を作り出しているわけではありません。
つまり、たとえ体の中にがんがあったとしても、それだけで死に至ることはほとんどあり得ないのです。別の言い方をすれば、複数の臓器に転移があったとしても、転移巣が臓器不全を起こさなければ、ヒトががんで死ぬことはまずない、ということになります。
そこで注目していただきたいのが「天寿がん」の存在です。
■がんに気づかないまま老衰死する高齢者は多い
日本では今、「2人に1人ががんにかかる」と言われています。しかし、これは日本人が「一生のうちにがんと診断される確率」を述べたもので、すべての世代で2人に1人ががんにかかることを示しているわけではありません。
事実、公益財団法人がん研究振興財団がまとめた「がんの統計’19」を見ると、例えば日本人男性ががん(対象は全がん種)にかかる確率は、39歳までが1.1%、49歳までが2.6%、59歳までが7.7%、69歳までが20.9%、79歳までが41.5%と、歳を取るにつれて上昇し、80歳以降(生涯)では63.3%に達しています(女性の場合も同じ傾向)。要するに、がんにかかるリスクは加齢とともに急増していくというのが、「2人に1人ががんにかかる」という統計数字の本質なのです。
しかも、このデータは一生のうちにがんと診断される確率を示しているにすぎず、がんにかかっていることを知らずに天寿を迎えた高齢者はカウントされていません。このようなケースも含めた場合、高齢者ががんにかかる確率は「2人に1人」をはるかに上回る数字になると考えられるのです。
実際、老衰で死亡した高齢者を解剖すると、かなりの高確率でがんが見つかります。そして、がんにかかっていたにもかかわらず、本人も家族も医師もそうとは気づかぬまま、がんではなく老衰で亡くなった、すなわち天寿を全うできたという意味で、このようながんは「天寿がん」と呼ばれているのです。
■「治るか死ぬか」二択の間で見えてくる視点
天寿がんは「安らかに人を死に導く超高齢者のがん」と定義されています。
定義にある超高齢者とは男性なら85歳以上、女性なら90歳以上とされていますが、中には、亡くなる数カ月前から胃の不調や食欲不振を訴え、死後の解剖の結果、胃の出口付近にがんがあったことが判明した、といったケースもあります。この場合、死因は老衰ではなく胃がんによる消化管の通過障害だったということになりますが、外形的にはだんだんとものが食べられなくなって老衰による自然死を迎えたように見えるのです。
このようなケースも含めて考えると、天寿がんは「超高齢者を最小の障害で死に導くがん」と定義づけることもできるでしょう。
しかし、私がここで問題にしたいのは安らかな死に方ではなく、天寿がんが物語る真実から見えてくる新たな視点です。
がん患者の多数を占める固形がんの場合、原発巣の摘出手術からおおむね5年が経過して、他臓器や遠隔リンパ節などに再発が認められなければ「がんは治った」と判定されます。一方、手術後に再発した場合、あるいは最初にがんが見つかった時点で転移が認められた場合には「がんは治らない」と判定されます。
後者の場合、「治らない」という判定は事実上の死の宣告にあたること、すなわち「治らない」は「死ぬ」と同義です。
突き詰めて言うならば、標準がん治療には「治る」か「治らない(死ぬ)」かの二択、2つの結論しか存在していない、ということになるのです。
■小康状態のまま天寿を全うする場合もある
ところが、天寿がんの存在は、「治る」と「治らない」の間にはもう1つの概念、それらの間に位置する概念があることを教えています。
では、「治る」と「治らない」の間にある概念とはどのようなものなのでしょうか。
そこで浮上してくるのが「寛解」というキーワードです。
寛解は「根本的な治癒には至らないものの、病勢が進行せずに安定している状態」のことです。IV期の固形がんを例に取れば、転移巣が致死的な臓器不全を起こすほどには増悪せずに小康状態を保っている状態です。
この点は転移巣が1つであっても複数であっても同じで、寛解状態にある限り、患者ががんそのものによって死に至ることはありません。
同様に、天寿がんが超高齢者を苦痛死に至らしめることはほとんどありません。前述したように、がんにかかっていたにもかかわらず、本人も家族も医師もそうとは気づかぬまま、老衰死のように安らかに亡くなっていくのです。
これを寛解という言葉を使って言い換えれば「がんが寛解状態をずっと保ったまま、老衰死のように天寿を全うした」ということになります。
実は、標準がん治療にも寛解という概念がないわけではありません。
例えば、延命のための抗がん剤治療でも、がんが消失した場合の完全奏効(CR=コンプリート・レスポンス)、あるいはがんが縮小した場合の部分奏効(PR=パーシャル・レスポンス)という概念が存在します。
■根本的な治癒は無理だが、悪化することもない
しかし、すでに指摘したように、ほとんどの場合、がんは抗がん剤に対する耐性を獲得し、かつ、猛烈な勢いでリバウンドしてきます。つまり、抗がん剤治療における完全奏効や部分奏効は一時的な寛解状態にすぎないのです。
寛解状態が一時的なもので終わってしまうのでは意味がありません。標準がん治療の限界を乗り越える全く新しいがん治療の地平を切り拓くには、天寿がんのように寛解状態がずっと続く状態を実現させる必要があるからです。
そこで次なるキーワードとして浮上してくるのが「劇的寛解」という言葉です。
この言葉は、長年にわたる臨床や研究の末に私が用い始めた造語ですが、同時期に米国の腫瘍内科学の研究者として知られるケリー・ターナー博士も、日本で翻訳出版された『がんが自然に治る生き方』(プレジデント社、2014年)などの著書の中で、「Radical Remission(根本的な寛解=劇的寛解)」という概念を提唱しています。
寛解は「根本的な治癒には至らないものの、病勢が進行せずに安定している状態」のことですが、私はこの概念をさらに前進させる形で、劇的寛解を「標準がん治療ではおよそ考えられない寛解状態が長く続くこと」と定義しました。
つまり、この劇的寛解こそが、前述した「治る」と「治らない」の間に存在する、あるいはその間隙を埋める究極の概念なのです。
■「余命半年」の肺がん患者が3年後に現れた
実は、私が今述べた「劇的寛解」というオリジナルな言葉と概念に辿り着くキッカケを与えてくれたのはAさんという京大病院時代の患者さんでした。
私が京大病院呼吸器外科の教授を退官(2007年)して間もなくのことです。退官から数年の間、私はいくつかのクリニックや中規模病院で外来を受け持っていましたが、その私の外来にAさんがひょっこりと姿を現したのです。
私はAさんのお元気そうな様子を目の当たりにして驚きました。というのも、Aさんはすでに肺がん(原発巣)が体のあちこちに転移していた患者さんで、およそ3年前、私が京大病院で手術不能と診断していた末期の患者さんだったからです。その後、Aさんは延命のための抗がん剤治療や放射線治療を受けていましたが、私は初診の段階で「余命は半年くらいだと思います」とも伝えていたのです。
そんな経緯があったものですから、たいへん失礼ながら、私は「Aさんはとっくの昔にお亡くなりになっている」と思い込んでいました。
私は眼の前に現れたAさんに虚心坦懐(たんかい)に尋ねました。
「Aさん、お元気そうで何よりです。それにしてもビックリしました。いったい、どのようにして、あの肺がんを乗り越えられたのですか」
すると、Aさんは次のようにおっしゃったのです。
「食事療法です。食事を変えたら、こうなりました」
■余命宣告から18年経ってもピンピンしている
Aさんはかつて酒とタバコをたしなんでいました。大好きだったその酒とタバコをキッパリとやめた上で、食生活の見直しに徹底的に取り組んだというのです。
Aさんが実践してきた食事療法はおおむね以下のようなものでした。
・1日あたりの総摂取カロリーを「1600キロカロリー以下」に抑える
・炭水化物の主な摂取源は白米ではなく「玄米」とする
・タンパク質の主な摂取源は「豆腐(植物性タンパク質)」とする
・「野菜」や「果物」を多く摂取する
・緑黄色野菜をすり潰した「ジュース」を飲む
・「水分」を多く摂取する
実は、その後、Aさんは私が2011年に開設したクリニック(からすま和田クリニック。京都市中京区)を受診され、今(2022年1月現在)も当時と全く変わりなくピンピンしておられるのです。
京大病院時代、私が「余命半年」を宣告した時点から数えれば実に18年です。Aさんのケースは標準がん治療ではおよそ考えられない超長期生存例ですが、おそらく現在の良好な状態を保ったまま天寿を全うされるのではないかと私は見ています。
いずれにせよ、Aさんは「劇的寛解はどうすれば得られるのか」について、私に身をもって教えてくれた最初の患者さんだったのです。
———-
からすま和田クリニック院長、京都大学名誉教授、一般社団法人日本がんと炎症・代謝研究会代表理事
1943年大阪市生まれ。1970年京都大学医学部卒業。医学博士。京都大学胸部疾患研究所、同大学再生医科学研究所を経て同大学大学院医学研究科器官外科(呼吸器外科)教授。京都大学を退職後、2011年にからすま和田クリニックを開設。主な著書に『がんに負けないからだをつくる 和田屋のごはん』『がんに負けないこころとからだのつくりかた』(以上共著、WIKOM研究所)、『がんを生き抜く最強ごはん』(毎日新聞出版)、『がん劇的寛解』(角川新書)などがある。
———-